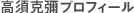少年・高須克彌
いつもいじめられていた。
それでも、いつも前向きだった。
防空壕の中で凍死しかけて生まれてきた。
高須克彌の人生は、始まりから劇的だった。太平洋戦争末期の1945年1月、日本の上空を米軍機が飛び交っているさなかに、家の庭に掘った防空壕の中で産声を上げた。しかし、凍てつく寒さの中で、その産声はすぐに止み凍死しかけてしまったのだ。高須家に100年ぶりに生まれた男の子を、祖母である高須いまが必死になって手を尽くし、やっとのことで一命を取り留めたという。こういった出来事もあってか、祖母からは「おまえは特別な子供なんだ」と言われ続けて育てられた。
少年時代のあだ名は、白豚くん。
戦後の日本、誰もが貧しく飢えて荒くれていた時代。高須克彌の生まれた愛知県の一色町にも、地回りの“やくざ”がはびこり、ばくち打ちが盛んだったという。地元の大地主だった高須家は、戦後の農地解放で多くの土地を手放したとはいえ、それでも医者としてまだまだ裕福な家庭だった。なに不自由なく育てられた高須克彌は、いわゆるおぼっちゃまで、色が白く、太っていた。それはすさんだ町の悪ガキたちにとって、格好のいじめの対象となった。みんなから白豚と呼ばれ、住所を書かずに「高須白豚くん」と書いた年賀状が届いたこともあった。高須克彌が大人になってから、白豚のキャラクターをコレクションするようになったのは、過去の辛い思い出をも楽しい思い出に変えようとする、常に圧倒的ポジティブな発想からかもしれない。
高須家には小学校の先生が家庭教師として通っており、勉強は常に先に進んでいた。もともとの素質もあったのだろう、小学校1年の時にはすでに高学年の教科書が理解できたという。しかし、それもいじめられる原因となった。授業が退屈でしょうがなく、先生が間違えるとそれもあからさまに指摘したり、先生が教えようとすることを先回りしてみんなに教えたりして、浮いた存在になってしまっていた。
ノートに落書きされ、石をぶつけられ、服は破かれる。それでも高須克彌は、いじめる奴らの軍門に下ることはなかった。喧嘩は弱くても、意志は強かった。いじめられてもいじめられても、“口撃”し続けた高須少年。精神的には、いじめる側よりも優位な気持ちに立っていたのだと言う。祖母の教えを信用し「僕は特別なんだから」と思いこんでいたのだ。この少年期の体験が、どんな偏見にさらされ逆境に立たされても、自分の意志を曲げずに前向きに突き進んでいく、高須克彌の生きる姿勢を養ったのかもしれない。
それでも一色町を愛している。

小学校時代の担任の証言によると、高須少年は小学校2年の頃から、自分のことを医者の卵と言っていたらしい。医師として働く母の姿を見て、患者に慕われる地域医療に貢献したいという決心を、子供ながらに固めていたのだった。いじめられていた町、でもこの町のために医療で貢献したいと思っていたのだ。
少年時代にいじめられた思い出しかない故郷の一色町。それでも高須克彌は、この町を愛し、今でも頻繁に帰ってくる。彼を迎えるのは、かつてのいじめっこ。「かっちゃん、昔は楽しかったのう」と笑顔で寄ってくる。その男性は、櫂で突きまくって痛めつけたことなど、まるでなかったかのようだ。高須克彌も50年もたてば全ては懐かしい思い出だと、暖かく受け入れている。